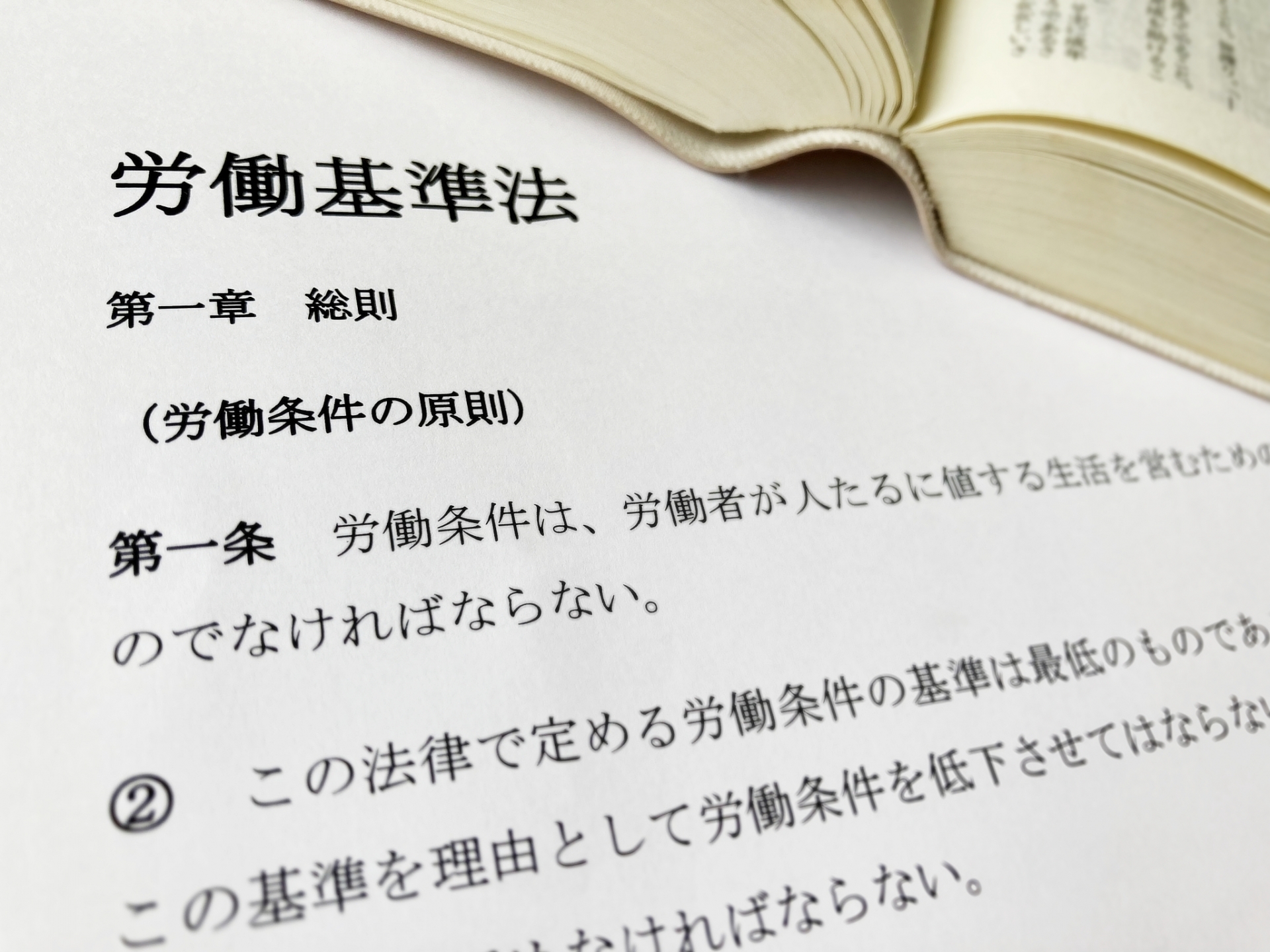第18条 (強制貯金)
1 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
この条文は、「会社が勝手に労働者のお金を預かって貯金させること」を制限するルールです。
昔は会社が給料から勝手に天引きして貯金させること(強制貯金)があり、労働者が自由にお金を使えない問題があったため、法律で規制されました。
① 強制貯金の禁止
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
・会社はうちで働くなら毎月貯金しなさいと強制したり、勝手に貯金契約を結ばせたりしてはいけません。
・労働者が自分の意思で貯金するならOKですが、強制はNGです。
③管理ルールを明示する義務
管理規程を作り、労働者に周知する。
・「どんなルールで預かるか」を明文化し、作業場に掲示するなどして全員が見られる状態にしなければなりません。
②管理する場合は労使協定+届出が必要
管理する場合は、労働組合か労働者代表と協定を結び、行政官庁に届け出る。
・労働者が希望して会社に預ける場合(たとえば社内預金制度)は、労働者の代表と書面で協定を結び、労基署に届ける必要があります。
④利子をつける義務
預金扱いなら利子をつける。利率が低すぎる場合は厚生労働省令で定める利率を保証。
・会社が貯金を預かるなら、銀行のように利息をつける必要があります。
・利息が極端に低いときは、法律で定めた最低利率で計算したものとみなされます。
⑤労働者が請求したら返還する
労働者が返還を請求したら、遅滞なく返還。
・労働者が「お金を返して」と言ったら、すぐに返さなければなりません。
⑥行政官庁による中止命令
労働者に不利益がある場合は、行政官庁が中止命令を出せる。
・会社がこのルールを守らずに労働者に不利益を与えていると、労基署が「もう貯金を預かるのをやめなさい」と命令できます。
⑦中止命令後は速やかに返還
中止命令が出たら、すぐに返還。
・命令を受けた会社は、すぐにお金を労働者に返さなければなりません。